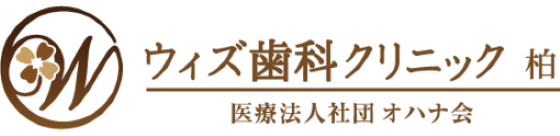小児矯正は後戻りが少ない?その理由と重要性を解説
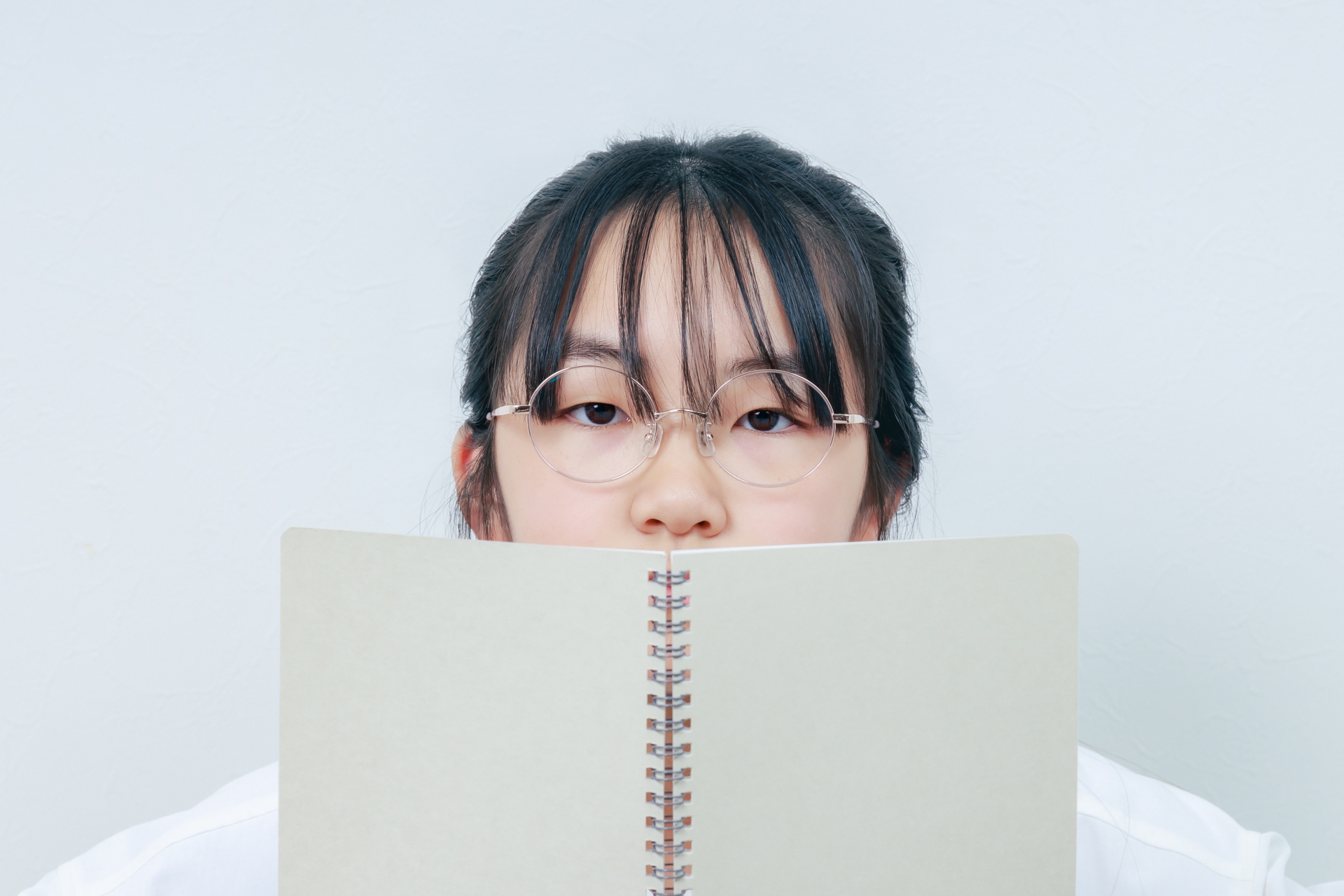
こんにちは!イオンモール柏の向かいにあるウィズ歯科クリニックの小児歯科医の根本です。
お子さまの歯並びや噛み合わせが気になる親御さまの中には、「小さい頃から矯正を始めると後戻りが少ないって本当?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は、小児期に矯正を始めることで、成長を味方にしながら歯列や顎のバランスを整えることができ、矯正後の後戻りが起こりにくくなるケースが多く見られます。そこで本コラムでは、小児矯正が後戻りしにくい理由や、注意すべきケース、さらに第二期治療との違いについて詳しく解説していきます。
小児矯正は後戻りが少ない理由

◎そもそも小児矯正とは
小児矯正とは、成長発育期のお子さまに対して行う歯科矯正治療のことで、大きく「1期治療(骨格的な改善)」と「2期治療(歯列の最終仕上げ)」の2段階に分かれています。特に1期治療は、6歳から10歳ごろの混合歯列期に開始されることが多く、この時期は乳歯と永久歯が混在する段階で、歯並びだけでなく、顎の骨の発育にも大きな影響を与えるタイミングです。
1期治療では、歯列の乱れの根本的な原因である骨格の不調和や口腔習癖を早期に是正し、理想的な永久歯列へスムーズに移行できるよう導きます。単なる歯の位置を整えるだけでなく、咬合誘導や呼吸機能、舌の位置など、多角的な視点からのアプローチが求められます。
◎成長を利用できる1期治療の利点
この時期の最大の強みは、顎の成長がまだ活発であるため、骨格自体に働きかけることが可能な点です。たとえば、上顎の横幅が狭いお子さまには、拡大床や急速拡大装置を使用して上顎の成長を正しい方向へ促し、歯列弓の幅を確保することで将来的な叢生(歯の重なり)を予防できます。
また、上顎前突(いわゆる出っ歯)や下顎前突(反対咬合・受け口)など、骨格性の問題に関しても、成長のタイミングを見極めた矯正的介入により、比較的少ない力で骨の形態そのものを調整することが可能です。これにより、無理な歯の移動を避け、自然な咬合関係を構築できるため、矯正後の後戻りを起こしにくくなります。
さらに、成長に合わせた治療を行うことで、将来的に2期治療の必要性を減らしたり、治療期間や歯の移動距離を最小限に抑えられたりする場合もあります。これは、成人矯正では得られない小児矯正ならではの大きな利点です。
◎歯周組織の適応力が高い時期
小児期は、歯を支える組織である歯槽骨や歯根膜、歯茎といった軟組織が未成熟かつ柔軟性に富んでおり、歯の移動に対して適応が早いという特徴があります。特に歯槽骨は骨の再構築能力(リモデリング)が高く、新しい位置に移動した歯を速やかに支持できるように変化します。
このため、歯の移動後にその位置を保持しやすく、長期的な安定が得られやすいのです。逆に成人では、骨の再構築能力が年齢とともに低下しており、歯の移動後も安定するまでに時間を要し、後戻りのリスクが高くなります。
また、歯肉の厚みやコラーゲン含有量が多く、炎症に対する耐性も高いため、矯正治療中の歯周トラブルが起こりにくい点も、後戻りの抑制に寄与しています。
◎習癖の改善と早期対応
お子さまの歯並びに影響を与える要因として、口呼吸や舌突出癖、指しゃぶり、異常嚥下爪を噛むなどの習癖が挙げられます。これらは歯や顎の成長に悪影響を与えるだけでなく、矯正後の後戻りを招く大きな要因です。
1期治療では、これらの習癖を早期に発見・介入することで、骨格と筋肉のバランスを整え、安定した口腔環境を作り出すことが可能です。たとえば、舌癖がある場合は舌圧が前歯を持続的に押し出してしまうため、出っ歯や開咬を引き起こします。MFT(口腔筋機能療法)や舌のポジショニングの指導を組み合わせることで、歯列への負荷を根本から改善できます。
加えて、アレルギー性鼻炎などによる慢性的な口呼吸が原因で顎の発育に偏りが生じているケースでは、耳鼻科と連携しながら包括的に治療計画を立てる必要があります。単に装置を使うだけではなく、口腔機能全体の改善が小児矯正成功の鍵となります。
小児矯正でも後戻りしやすい子の特徴

次に挙げるような特徴をもつお子さまは、小児矯正で後戻りしやすいため注意が必要です。
◎習癖が継続している場合
先述したように、舌の位置異常や口呼吸などの習癖が続いているお子さまは、矯正後も歯列に悪影響を与える可能性があります。たとえば、舌で前歯を押す癖があると、出っ歯傾向(上顎前突)が再発しやすくなります。
そのため、矯正治療中はもちろんのこと、治療後も生活習慣や舌のトレーニングを通じて、正しい機能が維持できているかを確認することが重要です。
◎顎の成長が不十分な場合
成長期における顎の発育は個人差が大きく、特に下顎の成長が遅れている場合や、顎の左右差が大きい場合には、歯列矯正後に咬合バランスが崩れやすくなり、後戻りのリスクが高まります。
このようなケースでは、1期治療の後に継続的な経過観察が必要であり、適切な時期に2期治療を行うことで、歯並びの安定性を保つことができます。
2期治療は後戻りする?

小児矯正の仕上げの段階である2期治療では、後戻りするリスクも相応に高くなります。
◎2期治療とは何か?
2期治療は、永久歯がすべて生えそろった後、具体的には中学生以降に行う歯列矯正です。歯を理想的な位置へ移動させることが主目的で、ワイヤー矯正やマウスピース型矯正装置などを用います。
この段階では顎の骨の成長がほぼ完了しているため、歯の移動には成人矯正と同様の生力学的アプローチが必要になります。
◎2期治療で後戻りが起きる理由
2期治療では、歯を支える骨や周囲の組織の適応力が小児期よりも低いため、矯正後に元の位置へ戻る「後戻り」が起こりやすい傾向があります。これは、以下のような理由によります。
・歯根膜や歯槽骨が小学生の時期よりもやや硬く、移動後の位置に適応するまでに時間がかかる
・口腔習癖や舌の癖がすでに定着しており、再発しやすい
・顎の骨の成長が終了しているため、骨格的な改善が困難である
そのため、2期治療を終えた後は長期間の保定が必要となり、保定装置の種類や使用時間も成人矯正と同様に管理されます。
◎後戻りのリスクを減らすには
2期治療における後戻りのリスクを軽減するためには、まず1期治療で土台を整えておくことが有効です。1期治療で顎のバランスや悪習癖を改善したうえで2期治療に移行すれば、歯の移動量が少なくて済み、より安定した治療結果が得られる可能性が高まります。
また、保定期間中には定期的なメンテナンスや咬合チェックを受けることで、後戻りの兆候を早期に発見し、リカバリーを図ることができます。
まとめ
小児矯正は、お子さまの成長を利用しながら歯並びや顎の発育をコントロールすることで、矯正後の後戻りが少ないという大きなメリットがあります。特に1期治療は、顎のバランス調整や習癖改善など、歯列の土台づくりに焦点を当てた重要なステージです。
しかし、習癖が続いていたり、保定が不十分だったりすると、小児矯正でも後戻りが起こる可能性があります。また、2期治療は成長後に行うため、歯や骨の適応力が低く、後戻りのリスクが高まります。
だからこそ、小児矯正は早期に適切な治療を開始し、正しい生活習慣とアフターケアをしっかり行うことが大切です。お子さまの将来の歯並びや健康的な口元を守るために、専門的な診断と長期的なフォローを大切にしていきましょう。
千葉県柏市のウィズ歯科クリニックでは小児歯科専門の医師が在籍しております。お子さまのお口のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
技術・接遇の追求
患者満足度日本一の歯科医院を目指します
『一般歯科』『小児歯科』『口腔外科』『親知らずの抜歯』『矯正歯科』『審美』『歯周病治療』『口臭治療』『入れ歯』『歯の痛み』『無痛治療』『ホワイトニング』『インプラント』『フラップレスインプラント』『セラミック治療』『保育士託児』『相談室でのカウンセリング』『口コミ、評判』『分かりやすい説明』
柏、南柏の歯医者 ウィズ歯科クリニック 柏院
オフィシャルサイト:https://www.with-dc.com/
インプラントサイト:https://www.with-dc.com/implant/
お問合せ電話番号:04-7145-0002